キラキラネームの親は低脳だという意見があります。
読めない名前をつける親のレベルは教養と関係があるのでしょうか?
読むほうも、読まれるほうも、なかなか難しい問題があるこのキラキラネーム。
キラキラネームと親のレベルや教養についても以前からいろいろな考えがあり、それぞれが独自の意見を語っています。
実際のところは、どうなのでしょうか?
キラキラネームとは?読めない名前をつける親
改正戸籍法により、キラキラネームが今後どういう扱いになるか、本来の漢字と違う読み方がどこまで許されるか、場合によっては届け出時に認められない可能性も出てくるかも、と話題ですね。
4月に子供のクラスメイトの名前を見ると、読めない名前や、当て字で無理やり読ませる名前が必ずといっていいほどあります。
読めない名前をつける親は今も増え続けています。
どんな名前をキラキラネームというのか調べてみました。
ウィキペディアからの引用によると、
キラキラネームは、当て字で間違った読ませ方や、しばしば暴走族が好む発音に文字を当てはめたような名前 。
そもそも、民法には命名行為について規定がなく、命名に際しては、漢字は常用漢字表(2136字)と人名用漢字表(863字)の合計2999字であれば、自由に組み合わせて使える。さらに、戸籍の名の欄には漢字の読み方が記載されず、出生届に「よみかた」があるだけである。このため、難解な読み方や、キラキラネームを付けることができる
漢字って本当にたくさんありますよね。
英語はアルファベット26文字の組み合わせで表現できるのに、日本語はとても複雑です(>_<)
読み方も、英語ならひねりようがなく決まっているのに、日本語は自由に「よみかた」をつけることができます。
これがキラキラネームが流行りだした背景なんですね♪
『キラキラネームの大研究』という本があります。
この著者の伊東ひとみさんによると、「キラキラネーム」と呼ばれる名前が出てきたのは1995年頃からで、その後2000年代に急激に増え、2010年前後に全盛期となったといいます。
こちらの記事で、キラキラネームが始まったきっかけを詳しく紹介しています。
さて、読めない名前をつける親、キラキラネームの親は低脳なのか?
この話題はひろゆき氏抜きには語れませんね。
キラキラネームと親の特徴 親のレベルや教養は関係がある?
キラキラネームと親のレベルや教養とは関係があると思いますか?
「2ちゃんねる」開設者のひろゆきさんの連載コラムからの引用を掲載します。
―[ひろゆき連載コラム「僕が親ならこうするね」]―
他人が読めない、キラキラネームをつける親がバカな理由
子どもが産まれて、最初に親が悩むのが名前決め。キラキラネームなるものをつける親がいますが、僕は親がやってはいけない代表格だと思うのです。 キラキラネームをつけられた子どもは、将来的にデメリットやハンディを背負う可能性が高くなります。他人が読むためにつける名前が読めないって時点でハンディですが、それがイジメに繋がるケースもあります。イジメであれば本人次第で何とかできる部分もありますが、社会人になるとき、就職活動で不利になることがあるのです。
(中略)
芸能人の子ども。奇抜な名前でも、将来的に芸能人として生きていける可能性は高いので、むしろキラキラネームが相手にインパクトを与えます。
(中略)
でも、多くの人はそうはいきません。そう考えると、親がキラキラネームをつけた時点で、その努力やハンディを子どもに強いるのはあまりに厳しい。 このデメリットを想像できない親は頭が悪くないですか? 最近の研究結果では知能は遺伝することが判明しています。全員とは言いませんが、キラキラネームの人は頭が悪い可能性を孕んでいるとも言えてしまうわけです。
ひろゆきさんは、読めない名前をつける親、つまりキラキラネームをつける親は、頭が良くない、という意見ですね。
教養とは少し違うのかもしれませんが、レベルが低い、ということでしょう。
否定的な意見であることは確かです。
子供の人生にわざわざハンディをつけるのは、子供の幸せを願うはずの親がやることではない、ということでしょうね。
確かに普通に読める名前の履歴書と、キラキラネームの履歴書を手にしたとき、どちらを選ぶかと聞かれたら、前者を選ぶのが一般的だと思います。
その子の育ってきた背景や環境を想像してしまうのもわかります。
実際会って話してみると、「なんだ、イメージと違うな」といい印象に好転するのは普通の名前の方よりもキラキラネームの方でしょうけど、第一印象が履歴書で決まる就職試験などには不利だということは簡単に想像がつきます。
ただ可愛らしい読み方をつけるキラキラネームくらいなら愛嬌もありますが、突拍子もない読み方の名前だと、確かにいろいろな場面で苦労しそうですね。
実際改名した方もいらっしゃるほどです。
一方でこんな意見もあります。
ひろゆきさんとは少し観点が違うのですが、茂木健一郎さんは
「キラキラネームをつける親を教養がない、という人こそ人間としての教養がない」と言っています。
ここでいう教養は、学問での教養ではなく、人としての教養で、人の事情をとやかく言うものではない、ということでしょう。
”4649”を ”よろしく”と当てる例を挙げ、万葉のころから当て字をする文化がある、いうようなことも言われています。
でもやっぱり程度というものはあると思います。ただの単語ではなく、一生つきあっていく名前ですから。。。
キラキラネームのまとめ

親のレベルの高さや教養がある、ない、ではなく、考えるべきは子供の幸せ。
もし、とんでもないキラキラネームを持った人に出会ったとしても、親ではなく、本人をきちんと見つめてあげられる、人間としての教養を持った人になりたいものです。
そして、キラキラネームを持つ人の理想は、キラキラネームに誇りを持ち、武器にできるくらいの人ですね。
なにはともあれ、改正戸籍法では、従来なかった「読みがな」が追加されることとなりました。
デジタル化を目指す政府は、特にマイナンバーカードの定着に必死です。
戸籍に読みがながつくことで戸籍データが検索しやすくなり、近い将来、戸籍とマイナンバー、さらには金融機関の口座情報をスムーズに連携させようというのが狙いのようです。
キラキラネームが今後どういう扱いになるか、本来の漢字と違う読み方がどこまで許されるか、場合によっては届け出時に認められない可能性も出てくるでしょう。
今後の「キラキラネーム」の名前の読み方に変化があるのか見守りましょう。
尚、キラキラネームが始まったきっかけについては興味深いものがあります。
こちらの記事で詳しくお話ししていますので、よかったらどうぞ。
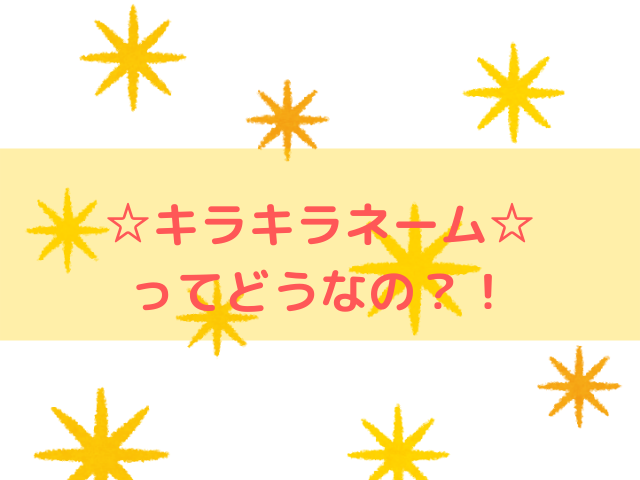

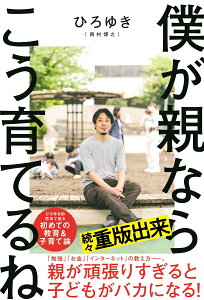

コメントを残す